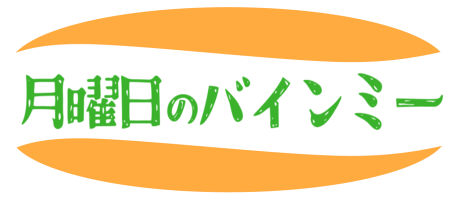留まることを知らない抹茶ブーム。そんな折、ホーチミン市内の至る所で、鮮やかな緑色の看板を掲げたドリンク店が急速に店舗数を増やしていることに気が付きました。
それが、2024年に設立された新興ブランド「Matcha Vibe」。ホーチミン市のみならず、ベトナム各地の都市部で店舗を増やしており、「100%日本から輸入した高品質な抹茶」 の使用を謳いながらも、看板商品の抹茶ラテを35,000ドンからという低価格で販売します。
日本産抹茶を使用した抹茶ラテはアッパーミドル帯以上のカフェで扱われることが多いですが、価格は大抵70,000ドン前後から。コストを抑えられるデリバリー専門店であっても、安くて50,000ドン前後からであり、「Matcha Vibe」の安さは目を引きます。
どんなものなのか、実際に店舗を訪れてみました。
「Matcha Vibe」、その戦略


まずは「Matcha Vibe」のメニューをご覧ください。
Matcha Vibeは、その製品品質を「Fuji基準」「プレミアム/上級(Thượng hạng)」 と位置づけ、メニューには「宇治、京都、日本産」と明記しているものもあります。これを信じるのであれば、価格は高騰するはずですが、同ブランドは抹茶ラテのSサイズを35,000ドンという中間価格帯に設定しています。
これを可能にしたのが、15年以上のF&B経験を持つ創業者である、チャン・ホン・チャン女史の手腕。店舗数が少ない創業初期の段階より、将来の大規模展開を交渉材料に、日本のサプライヤー(どこなんですかね)と「長期的、固定的、かつ独占的な輸入契約」を結ぶことに成功したのだそうで。
これにより、抹茶パウダーという主要コストが市場の価格変動から切り離され、凍結されたことになります。これが1つ目の戦略。
…なお、「Fuji基準」とは何ぞやという話。おそらく、特定の日本の茶園や抹茶ブランドの固有名詞ではなく、サプライヤーが海外市場向けに「日本産のプレミアムグレード」であることを分かりやすく伝えるために戦略的に設定した、マーケティング上の等級名(ブランディング)なのでは?と推測しておりますよ。お茶の産地を言われてもピンと来ないだろうけど、「Fuji」なら「富士山」を連想して、即座に「日本産」というイメージに繋がるでしょうし。
2つ目の戦略としては、「最適化されたマルチチャネル運営モデル」による「デリバリーファースト」の徹底。売上の70%以上が「Grabfood」などのデリバリーアプリ経由だそうで、ブランド側はフランチャイズ加盟者に対し「高価な立地や広大な店舗スペースに過度に投資する必要はない」と明言しています。
しかし、ブランド名で「Vibe(雰囲気)」を謳っておきながら、売上の大半がデリバリーとはどういうことなのか。実態は単なるデリバリーの拠点(クラウドキッチン)に過ぎないのか。どうなんだオイ!(豹変)
実店舗に行ってみよう

…ということで、ホーチミン市の中心地である旧1区の店舗・Nguyễn Bỉnh Khiêm店を訪れました。
オフィス街や観光地に近いエリアの大通り沿いにあるものの、間口は狭く、隣の薬局やローカル食堂の間に挟まれる形でコンパクトに収まっています。まさに「高価な立地には投資しない」 という戦略を体現していそう。

スペースの大半を占めるのは、木目調のL字型サービスカウンターと調理エリア。

イートインスペースもあるものの、レイアウトは明らかに、テイクアウト客の注文と、ひっきりなしに出入りするデリバリードライバーの注文を効率的に処理するために最適化されているように見える。この店舗が提供する「Vibe」は、決してカフェでくつろぐためのものとは言えません。

お次は旧ビンタイン区・Nguyễn Văn Thương店。この周辺は、大学や住宅街が近いエリアです。こちらの店舗も、他のローカルビジネス(精肉店、ビューティーサロン)に挟まれる形で通りに面しています。

先ほどの店舗とは異なり、十分な広さ・奥行きが確保された内装。クッション付きの木製チェアと円形テーブルが4〜5セットは配置されていました。つまり、顧客が店内で時間を過ごすことを前提とした空間設計。

この店舗は、デリバリー拠点としての機能も持ちつつ、近隣の住民や学生がくつろぐ「ローカルカフェ」としての「Vibe」を同時に提供する、ハイブリッド型のフォーマットと言えます。

これら2店舗の比較から、Matcha Vibeは画一的な店舗展開をしているのではなく、「ビジネス街(中心街)=デリバリーハブ型」「住宅・学生街=ハイブリッド型」というように、立地の特性に合わせて店舗のフォーマットを使い分けている可能性が示唆されます。
…まあ、フランチャイズオーナーの意向と言ってしまえばそれまでなのだけど(身も蓋もない)。
本当に日本産?実飲してみた
では実飲。今回はスタンダードな「Matcha Latte」と、製法が異なる「Cold Whisk Matcha Latte」をMサイズで注文し、比較しました。

まずは「Matcha Latte」45,000ドン。ミルクと抹茶の層が鮮やかに分かれています。抹茶の色は、安価な抹茶によくある人工的な青緑色ではなく、深みのある自然な緑色です。

まずはかき混ぜずに、抹茶の層の部分を一口。特に粉っぽさはない。中国産・台湾産抹茶に見られる香料っぽさが無いので日本産というのは正しいように思えます。一方、苦み・渋みの輪郭がはっきりしていながら、特有の旨味や甘みは感じられない。なんというか…薄い。
メニューによると、追加料金を支払うことで「Ceremonial(セレモニアルグレード)」にアップグレードできるとのことでした。裏を返せば、おそらく通常メニューに使われている抹茶は、製菓用など加工を前提した抹茶なんじゃないかなあ。もちろん、製菓用抹茶を飲用に使用しても何ら問題はありません。むしろ牛乳と混ぜても風味が負けない強さがあるので、こちらの方が抹茶ラテには向いているとも言える。
だもんで(静岡弁)、抹茶本来の風味を味わおうとして無糖を選んじゃうとガッカリかも。微糖にするのが一番バランス良くて美味しいと思います。

続いて「Cold Whisk Matcha Latte」。こちらはMサイズ50,000ドン。メニューによれば「抹茶を直接ミルクとウィスクする(点てる)」製法です。

通常の抹茶ラテと比べて、抹茶層がより泡立ち、ミルクとの境界が乳化しているように見えます。
撹拌によって空気が含まれるため、抹茶ラテよりも明らかに滑らかでクリーミーな質感が生まれているのが特徴。

この違いによる口当たりの向上は、5,000ドンの価格差に見合う価値がありそう。こちらも微糖をおすすめします。
まとめ。「Vibe」とは何だったのか

急成長中の抹茶専門店「Matcha Vibe」をご紹介しました。
彼らが提供する「Vibe」とは、従来のカフェのような、物理的な空間や内装(座席の豪華さなど)を指す言葉ではないようです。
Matcha Vibeの「Vibe」とは、「100%日本産の本物の抹茶」 を「手頃な価格」で「手軽」に楽しむ…。そんな体験あるいはライフスタイルの雰囲気のようなものを、漠然と「Vibe」と表現したのではなかろうか。
なんにせよ、ベトナムのF&B市場における新世代カフェの戦い方を象徴する、面白いブランドだと感じましたよ。